
 |
皇軍慰問バザー展覧会現在の学園祭にあたる「バザー」が初めて開催されたのは、大正14年3月の卒業式のあとでした。 昭和初期には、バザーと共に展覧会も開催されていました。この写真は、昭和12年のバザー・展覧会で、 時節柄、「皇軍慰問」の名前が必要でした。 |
 |
老校長岡本巌先生ご逝去昭和17年5月18日の朝、宿直室で昏睡状態となっていた老校長を、富郎先生が発見されました。 尿毒症でした。翌19日の文部省による「学事総合視察」を病床で迎えることとなってしまいましたが、 「全国的模範校」に指定され、老校長の長年のご努力が報われました。その約1ヶ月後の6月16日、 岡本巌先生は76歳のご生涯を閉じられました。 |
 |
岡本巌先生の学園葬昭和17年6月26日、西遠・淑徳両校関係者による巌先生の校葬がしめやかに行われました。 現在でも、老校長先生のご命日には、全校生徒が黙祷を捧げています。また、入学や卒業の時には、 墓前に入学の誓いや卒業の報告をしています。 |
 |
畑になった戦時中の校庭昭和17年、生徒は近郊の農家に勤労奉仕に出かけたり、校庭を畑にして、食料増産に励むことになりました。 この頃の生徒たちの服装は、セーラー服からネクタイは消え、スカートの代わりに「もんぺ」、 肩からは防空頭巾と布製の袋を左右にかけ、足にはズック靴というものでした。 |
 |
「学徒動員令」下される昭和19年7月25日、西遠と淑徳にも学徒動員令が下されました。2年生以上の生徒は軍需工場などに配属させられました。 動員された生徒たちは、かすりの着物にモンペを履き、防空頭巾をかぶり、 肩からは教科書や非常食を入れた救急カバンを下げるといういでたちでした。 この写真は、昭和20年1月、東洋木工の工場へ動員されたときのものです。 |
 |
焼け野原となった浜松の街昭和20年になると、アメリカ軍の爆撃機B29による空襲が激しさを増し、浜松の街は焼け野原となってしまいました。 その中で、西遠の動員学徒29名と引率の先生1名が犠牲となりました。 |
 |
戦災をまぬがれた本館昭和20年8月15日、日本の敗戦という形で、数多くの犠牲を出した戦争は終わりました。 幸運にも、西遠高女の校舎は焼失をまぬがれました。しかし、校庭は畑となったままで、教科書はなく、 ノートや鉛筆もありませんでした。 |
 |
図書館となった修身堂戦後の日本の教育改革にともなって、昭和22年4月には新制中学校が併設され、翌23年4月には、 西遠と淑徳を合併する形で新制高等学校が設置され、校名を「静岡県西遠女子学園中学校・高等学校」としました。 また、「修身」の授業がなくなり、修身堂は、昭和22年、図書館として改修されました。 |
 |
昭和24年に建設された体育館昭和24年、校地の北西の一角に体育館が建設されました。当時は体育館をもつ学校はほとんどなく、140坪という広さは、 当時としては東海地方第一のものでした。その内部には、佐々木松次郎先生の「円盤を投げる人」の壁画が掲げられていました。 |
 |
殉難教員学徒合同慰霊祭敗戦後の荒廃から立ち直り、平和条約発効によって日本が再び独立を取り戻した昭和27年、 戦争中に花もつぼみのまま散った動員学徒29名と引率の先生1名の御霊を慰めようと、爆撃のあった5月19日、 当時の同期生を招き、在校生も参加して、慰霊祭が講堂で行われました。 |
 |
講堂塔屋に備えられた大時計昭和27年、講堂の大改修が行われました。それに併せて、講堂の南側に鐘塔と時計塔を兼ねた塔屋が増設されました。 この塔からウェストミンスターの鐘の音が流されました。また、生徒たちは、この塔の大時計を見て、時刻を知りました。 |
 |
湯川秀樹博士ご夫妻来校昭和29年10月29日、ノーベル物理学賞を受賞された湯川秀樹ご夫妻が西遠を訪れ、湯川博士は「科学者としての体験」、 すみ子夫人は「欧米の婦人」と題して講演を行いました。 |
 |
創立50周年記念館の竣工昭和30年、創立50周年を記念して、学園最初の鉄筋コンクリートの建物である記念館が建設されました。 1階には300人収容の大食堂があり、その正面には佐々木松次郎先生デザインによる見事な古代エジプト調のモザイク壁画がはめ込まれていました。 この大食堂では、調理実習の試食や食事マナー指導が行われました。 |
 |
創立50周年記念式典昭和30年、施設の新増築や改修を終えて「学園」と呼ぶにふさわしい環境が整い、創立50周年を祝う記念行事が行われました。 10月には記念式典が挙行されました。 |
 |
陸上競技部インターハイ総合優勝昭和30年と34年の二度のインターハイでの総合優勝をはじめとして、陸上競技部は様々な大会で輝かしい成績を残しました。 先輩方が残した伝統は、後輩たちに引き継がれ、現在まで続いています。 |
 |
「愛の灯」像の除幕式(昭和34年)昭和34年5月19日、殉難学徒慰霊の像として建立された「愛の灯」像の除幕式が行われました。 遺族・同期生をはじめ、同窓生・在校生・教職員など学園関係者が多数集まり、平和を祈って「動員学徒に捧げる歌」を歌い、 平和への誓いを新たにしました。 |
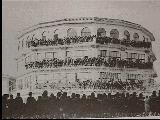 |
高校館扇形校舎落成(昭和35年)昭和35年、校地の北東部に鉄筋コンクリート造り4階建ての扇形校舎が高校館として建設されました。 当時の高校のクラス数は各学年6学級ずつで、教室は全校に散在していましたが、扇形校舎の完成で、 木造二階建ての旧校舎と併せて、高校の教室がまとめられました。これは、進路別の学級編成を行う上で好都合でした。 |
 |
富郎先生、藍綬褒賞を受賞昭和36年、岡本富郎先生が教育文化功労者として藍綬褒賞を国から授与されました。 |
 |
昭和40年頃の学園のたたずまい歴史的な木造建築である旧本館・旧講堂と鉄筋コンクリート造の扇形校舎や昭和40年に完成したばかりの第2中学館(現在の南館)が同居していた頃の写真。 |