
 |
昭和2年に新装された大講堂はじめ西遠高女には講堂がなく、3つの教室の仕切戸を外して大教室としていたものを「仮講堂」と呼んで集会などに使用していましたが、 大正15年9月、台風で倒壊してしまいました。これを機会に直ちに講堂の建設に着手し、昭和2年3月に完成したのがこの大講堂です。 |
 |
夏服の西遠高女の生徒たち昭和2年、正門を出て家路につく西遠高女の生徒たち。この姿は、当時の浜松の若い男性に評判となり、 生徒の登下校時に見物者が多数現れたとのことです。 |
 |
西遠と淑徳の合同研修旅行昭和2年の研修旅行での一場面。このころは、西遠高女と淑徳女学校合同で、関西方面および伊勢神宮への4泊5日の修学旅行が行われていました。 西遠の制服はすでに洋服(ワンピース)になっていましたが、淑徳はまだ和服でした。 |
 |
昭和4年頃の西遠高女の校舎昭和4年頃の西遠高女の校舎全景です。左端の大きな建物が昭和2年に完成した大講堂です。 |
 |
昭和4年、岡本欽先生ご逝去昭和4年2月、岡本欽先生が52歳の若さでお亡くなりになり、西遠・淑徳の両校は悲しみにおおわれました。 また、この年から始まった世界大恐慌が日本にも大きな不況をもたらし、西遠にも入学者減少の危機をもたらしました。 この危機を乗り越えようと奮闘されたのが、岡本家を継ぐこととなった青年教師若命富郎(わかみこととみろう)先生でした。 |
 |
若き日の岡本富郎先生昭和6年度の入学生がわずか17名という大きな危機を克服し、69名の新入生を迎えた昭和7年度、6月には、 巌先生に代わって岡本富郎先生が新校長に就任されました。このとき、富郎先生は32歳という若さでした。 姉妹校の淑徳女学校の校長は、引き続き巌先生がつとめられていましたので、この頃から巌先生を「老校長」とお呼びするようになりました。 |
 |
浜松淑徳女学校の生徒と校舎昭和7年、淑徳女学校の制服が和服からセーラー服になったのを記念して撮影したもの。 校舎のすぐ脇を走る東海道線の線路に沿って整列しています。 |
 |
昭和7年頃の割烹の授業入学生の数が減少から増加に転じ、富郎先生が校長に就任された頃の割烹の授業風景。本館内に割烹室がありました。 |
 |
昭和8年頃の音楽の授業昭和8年には、入学生の数は98名に増え、学園に活気が戻ってきました。元気な明るい歌声が響き渡っていたことでしょう。 |
 |
淑徳での徹底した裁縫授業淑徳女学校では、実科高女時代の伝統を受け継ぎ、裁縫の実技指導に教育の重点をおいていました。 今でいうと、被服系の専門学校にあたるでしょう。地域からの熟練度の高い裁縫教育に対する要望に応えようと、 徹底した裁縫授業が行われました。 |
 |
家庭寮教育のスタート昭和8年、新校長富郎先生が打ち出された第一の教育方針である「全人的な人間教育」を実践する場として、家庭寮が建設されました。 この年、現在の生活会館での指導の原点となる家庭寮教育がスタートしました。 |
 |
家庭寮を清掃する生徒たち家庭寮内では、すべて和服の生活で、寮母先生から厳しい中にもあたたかい実地指導を受けました。 富郎先生自らも、家庭寮教育の先頭に立たれ、時には夜の更けるのも忘れて、熱心に人生問題を語られることもありました。 生徒増から、昭和10年には第2家庭寮が増設され、さらに充実した家庭寮教育が押し進められました。 |
 |
完成した修身堂(昭和11年)「精神の教育を行うには、それにふさわしい環境が必要である」と考えた富郎先生は、修身堂の建設に着手されました。 夢殿を模した修身堂が完成したのは昭和11年のことでした。 |
 |
修身堂での富郎先生の訓話修身堂での修身教育は、主として富郎先生が、時には巌先生が担当され、女性の生きるべき道、 また広くは人間の生きるべき道を生徒に説かれました。修身堂は西遠高女の生徒の精神道場であり、 家庭寮教育と共に学園教育の柱となっていました。 |
 |
老校長先生古稀の祝い昭和11年、修身堂が落成したこの年に、全校をあげて岡本巌先生の古稀をお祝いすることになりました。 11月22日、同窓生や在校生たちがお金を出し合って製作した巌先生の胸像の除幕式が行われました。 |
 |
胸像前の巌先生・富郎先生とご家族除幕式を終えた胸像の前での岡本家ご家族の記念写真。胸像は、本館の玄関前に設置されていました。 |
 |
富士五湖巡り(昭和11年)昭和初期、西遠高女と淑徳女学校合同で富士五湖巡りが行われていました。この写真は、昭和11年に白糸の滝で撮影したもの。 西遠の生徒はセーラー服姿、淑徳の生徒は着物姿でした。 |
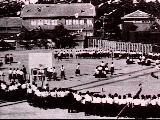 |
恩師を招待しての運動会小学校の恩師を招待しての大運動会の一場面。小学校恩師謝恩会は、昭和9年からスタートしました。 1年生が中心となって講堂で謝恩会を開催した後、全校あげての運動会にも参加していただいていました。 この写真は昭和12年のものです。 |
 |
鍛冶町通りを行進する西遠の生徒たち昭和16年12月8日、日本は太平洋戦争に突入し、西遠も重苦しい戦争の圧力を受けることになりました。 写真は、昭和12年3月10日の陸軍記念日に鍛冶町通りを行進する西遠の生徒たちを撮影したものです。 |